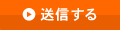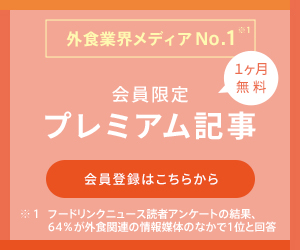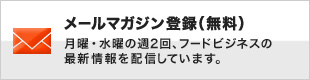やじうま速報
![]()
記事への評価
取材・執筆 : 安田正明 2025年2月6日
唐揚げ専門店の倒産は2024年に急減。競争激化や原材料高騰で小規模店が淘汰されたが、過当競争は緩和。唐揚げはブームから定着へ移行しつつある。帝国データバンクが調査。
<関連記事>

「唐揚げの失敗を取返す。ワタミが築地場外で3,000円の和牛串販売」 月商2,000万円は行けるネ。空前のインバウンド需要を取込む。
テイクアウトでも強い「から揚げ」大戦争! 外食大手が注力し、成功している理由
からあげ店企業、コロナで23%増えた。チェーン化が生き残りの鍵か。
持ち帰りを中心とした「唐揚げ店」経営業者の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は、24年に16件発生した。前年の9倍に急増した23年(27件)に比べて4割減少となった。倒産した事業者の多くが小規模で、閉店などを含めるとより多くの唐揚げ専門店が市場から退出したとみられるものの、淘汰ペースは24年に鈍化した。
コロナ禍の巣ごもりでテイクアウト需要が高まるなか、参入コストの低さやオペレーションの簡便さ、根強い人気を背景に、大手飲食チェーンから個人店まで様々な企業が唐揚げビジネスに参入し、短期間で競争が激化した。加えて、唐揚げの原材料として使用される輸入鶏肉をはじめ、調理に必要なキャノーラ油など食用油、小麦粉など各種原材料価格の高騰で製造コストが急上昇し、安価な原材料で利益を出す「唐揚げビジネス」の前提が崩れたこと、コロナ禍の収束に伴って持ち帰り需要の縮小といった経営環境の変化も重なった。
最近は、大手飲食チェーンが唐揚げビジネスを縮小・撤退するケースも出始め、利益面では厳しい環境が続きながらもコロナ禍直後の過当競争感は一転して緩和されつつある。また、コンビニ唐揚げや冷凍食品など、割安だった競合製品では値上げが相次いだ。生き残った専門店では、付加価値を付けることでリピート客の獲得に成功できている。急激なブーム拡大と縮小を経験しながらも定着したタピオカティーと似ているという。
ワタミがFCで300店舗を目標に2018年からスタートした「から揚げの天才」は現在、HP上で登録されているのは僅か7店舗のみ。
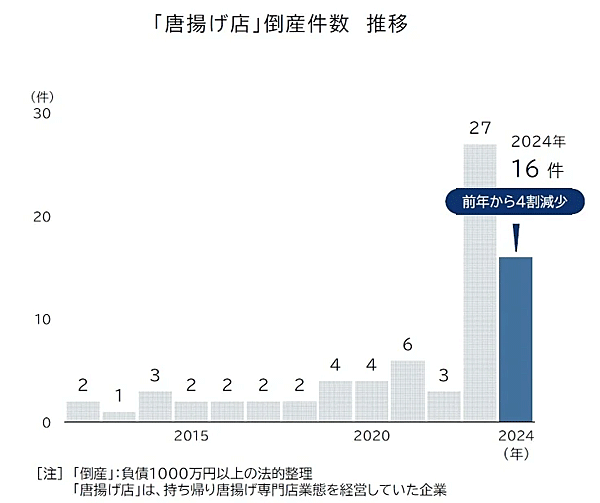

読者の感想
興味深い0.0 | 役に立つ0.0 | 誰かに教えたい0.0
- 総合評価
-
- 0.0