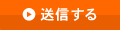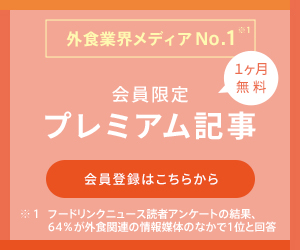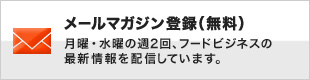フードリンクレポート
![]()
記事への評価
取材・執筆 : 南原卓也 2025年11月11日
【記事のポイント】
●「もったいない」から新発見した歳を重ねた親鶏だけが持つ旨味
●出汁にこだわる料理人も唸らせる「本鶏だし」の品質
●「本鶏だし」の汎用性を活かしたメニュー開発
<関連記事>
イオンイーハート「おひつごはん四六時中」、100店舗達成。03年創業、出汁ブームのはしり
「出汁業態やるなら彼に訊け」 出汁ブームの陰の立役者は世界最薄0.01mmの鰹節削り機発明者。ミシュラン星獲得店がこぞって導入
おでんバー「O'denbar うまみ」、4号店を赤坂に。ダシはインバウンドも巻き込むキーワード
日本で初めて国産カレー粉の製造に成功したのは「エスビー食品株式会社」。 1923年のことだった。その後、1950年に発売された「赤缶カレー粉」は、今も変わらず日本のカレー粉のスタンダードとして愛され続けている。
スパイスやハーブを使った商品のイメージが強い「エスビー食品株式会社」だが、アップサイクルとして、余剰分や廃棄予定の素材を使った商品開発にも取り組んでいる。その第一弾が「本鶏だし」だ。
これまで歳を重ねた親鶏だけが持つ旨味を捨てていたことに気づき、新発見した濃厚で深い旨味の美しい出汁。その味わいは、外食産業の最前線で活躍する料理人さえも唸らせる。
実際に「本鶏だし」を活用したメニューを提供している3店へ取材を行い、その本音を訊いてみた。
■佐藤養助 日比谷店(東京都港区西新橋)

佐藤養助 日比谷店
練る、綯う、延ばす、干す。
これは秋田県を代表する名産品「稲庭うどん」を作る工程だ。稲庭干温飩の原形が稲庭に伝わり、稲庭(佐藤)吉左エ門によってその技術が受け継がれ、研究と改良が重ねられ、製法が確立したのは1665年。今から360年も前の話だ。
親から子へ、子から孫へ。干温飩の技法は、吉左エ門家の一子相伝、門外不出の技として受け継がれた。その技が絶えることを危惧した吉左エ門は、二代目・佐藤養助へ特別にその技法を伝授。3日間かけて作る工程は、今もなお、すべて手作業で行われている。
秋田県内を中心に、東京都、香港に店舗を展開し、伝統の味とチャレンジ精神も併せ持つ老舗「有限会社 佐藤養助商店」。今回はその中から「佐藤養助 日比谷店」へ伺った。

東京エリアマネージャー 川村勝行さん
「試食をして驚きました。雑味がなく、鶏の旨味が濃厚。一口飲んで、これなら当店のうどんにも合うだろうと確信しました。」
そう話すのは、東京エリアマネージャー・川村勝行さん(以下、川村マネージャー)だ。
「佐藤養助商店」の稲庭うどんに惚れ込み入社を決めた川村マネージャー。その判断に間違いはなかった。1日限定15杯で販売している「本鶏だし白湯うどん」は、販売をスタートしてから毎日完売。販売3日目にして早くもリピーターが訪れるなど、上々のスタートを切った。しかも、注文した方の多くが、器にスープ一滴残すことなく完食している。
「うどんとのバランスを重視しつつ、本鶏だしの持ち味を活かすことに注力しました。ちょうど温麺の注文が増える時期と重なったこともありますが、当初の想像を上回る反響をいただいています。」(川村マネージャー)

うどんにとっての生命線は、出汁。それは稲庭うどんにとっても例外ではない。「佐藤養助 日比谷店」でも、厚削りと花鰹、2種類の鰹節と昆布、干し椎茸を使って出汁を引き、自慢の稲庭うどんに合わせたスープを作っている。
出汁にこだわる店にとって、既製品の「本鶏だし」を使用することに抵抗はなかったのだろうか?
「どんなにおすすめされても、店の味を落としかねるようなもの、店の看板に傷をつけるようなものだったら採用しません。少なくとも『本鶏だし』については、そんな心配はありません。
このレベルの鶏だしを、仮に自分たちで作ろうと思ったら、どれほどの手間や時間がかかるでしょうか。きっと相当な負荷がかかるはずです。『本鶏だし』に使用している素材も安心安全。鶏だしを使っている飲食店なら、どこでも検討してみる価値があると思います。」(川村マネージャー)
「本鶏だし」は、丸鶏は国産親鶏、鶏がらや鶏足も国産鶏。国産の鶏素材と水だけを使用して、3段圧力加熱製法(加圧、常圧、減圧)で長時間じっくり煮込んで作られる。その凝縮された旨味は、出汁にこだわる料理人からもお墨付きだ。
■魚豪商 コダマ(東京都港区新橋)

魚豪商 コダマ
"サラリーマンの聖地"と呼ばれ、新旧様々な業態の飲食店がひしめく新橋。そんな飲食最激戦区において、「ヤキオグループ」は今最も勢いのある一つといえるだろう。
「魚豪商 コダマ」は、同グループ初の大型路面店として2023年6月にオープン。仕入れ担当者が毎朝豊洲市場に足を運び、その日、一番状態の良い魚を目利きして仕入れる鮮度抜群の鮮魚を武器に、2年半にも満たない期間で、平日でも予約が困難な人気店へと急成長した。
「新鮮な魚介」「旬食材の天ぷら」「名物コラ豚(コラーゲン豚)」の三大名物も浸透し、その勢いはさらに増している。

五十嵐貴大さん
「本鶏だし煮込み」を開発した五十嵐貴大さん(以下、五十嵐さん)は、「本鶏だし」の品質と汎用性の高さについて強調する。
「ちょうど冬向けのメニュー開発に取り組んでいたときに、『本鶏だし』と出会いました。それまで候補としていたスープに『本鶏だし』を追加しただけで、味に深みとコクが加わり、全く違う料理になったんです。うちは魚が中心の店ですが、だからこそ肉を使ったメニューは注目されやすい。今回は狙い通りのメニューができたと自負しています。」(五十嵐さん)
「本鶏だし煮込み」は、販売当初「手羽大根」として販売していたが、思っていたような反響が得られなかった。
「日々勉強とチャレンジの繰り返し」と話す小玉邑椰店長は、よりストレートに特徴を訴求できるメニュー名を変更。それをきっかけに人気メニューへの仲間入りを果たすこととなる。
「寒い日でも、テラス席でコタツに入りながら食べる熱々メニューは最高です。旨味たっぷりの燗酒と合わせていただければ、体もポカポカ温まりますよ!」(五十嵐さん)

「『本鶏だし』を使ったことにより、スープは鶏の旨味がたっぷり。だから、手羽元はあえて焼いてからさっと煮込む程度にしています。それにより鶏の旨味と肉の食感を同時に楽しめるメニューになりました。『本鶏だし』を使ったからこそ実現できたメニューです。
汎用性が高いから、メニューの幅も広がりますね。例えば、『本鶏だしの茶碗蒸し』や、『本鶏だし』の中に鶏むね肉を入れて低温調理する『鶏ハム』も美味しそう。他のメニューとのバランスも考えつつ、色々チャレンジしてみたいです。」(五十嵐さん)
「本鶏だし」は、良質な鶏がら、肉からも旨味や脂が出る丸鶏、コラーゲンやヒアルロン酸などをたっぷり含んだ鶏足、さらには挽肉加工時に残る骨や筋とその周りの肉から無駄なく旨みを抽出している。その濃厚な鶏の旨味が、料理に深みとコクを与えてくれる。
■魚無双 トオダ(東京都港区新橋)

魚無双 トオダ
先述の「ヤキオグループ」の仕入れ担当・遠田俊介さん(以下、遠田店長)が店長を務め、2025年4月にオープンしたのが「魚無双 トオダ」だ。
築70年の木造古民家をフルリノベーションした和モダンな内装。黒を基調として、1階から2階まで続く大きな窓が印象的な外観。本格焼酎をメインとした店舗は、系列店初。常時50種類以上の焼酎をラインナップしている。
そのどれもが、これまでの同グループの店舗とは一線を画す「魚無双 トオダ」は、訪れる客層も独特。系列店では30〜40代の男性が中心の中、「魚無双 トオダ」を訪れる多くは20代〜30代。デートや女子会での利用も多い。

遠田店長
無類のカレー好きである遠田店長はかねてより、食事ではなく酒の肴になる"おつまみカレー"を作りたいと考えていた。その実現に一役買ったのが「本鶏だし」だった。
「和牛と本鶏だしで作るおつまみ秋野菜キーマ」には、同店の人気メニュー「和牛すじ煮込み」の脂と、「本鶏だし」の旨味、複数のスパイスを使用し、カレー店でも働くスタッフらと試作を重ねて作り上げた。
「『本鶏だし』も廃棄・余剰分を使ってアップサイクルした商品ですが、今回使用している和牛の上澄み脂も同じです。『和牛すじ煮込み』を作る上で、どうしても生まれてしまう余剰の脂を活用しました。美味しいのに使われず廃棄されるものって結構ありますからね。」(遠田店長)

旨みとコク、スパイシーさが際立つ「和牛と本鶏だしで作るおつまみ秋野菜キーマ」は、おつまみだということを意識し、ライスは盛られていない。バケットと一緒に食べるので、複数人でシェアしやすいのもポイントだ。
「おかげさまで、20〜30代の女性を中心に選んでいただいています。当店では、スパイスと焼酎を使ったリキュールも扱っているのですが、上品で爽やかな香りが心地よい『カルダモンソーダ』と一緒に召し上がってもらうのがおすすめです!」(遠田店長)
「本鶏だし」は、凝縮された旨味に加え、コラーゲンやヒアルロン酸、イミダゾールジペプチドなどのたっぷりの栄養素が含まれている。これらは女性を中心に好まれる栄養素であり、ターゲットとも合致する。
さらに、本来は使用されることがなかったものをアップサイクルしたメニュー開発。参考になる飲食店も多いはずだ。

外食産業を次の時代へとつなぐために、「アップサイクル」という視点は欠かせない。
しかし、どんなに意義があることでも、外食産業である以上、納得いく品質と選ばれる意味がなければ広まることはない。
サステナブルであることと、美味しさを両立させること。「エスビー食品株式会社」の「もったいない」から生まれた「本鶏だし」は、この大きな課題を解決し、食の価値を決めていく一つの答えなのかもしれない。
【取材店舗】
「佐藤養助 日比谷店」
東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビルB1
TEL:03-3595-6288
「魚豪商 コダマ」
東京都港区新橋4-19-10 タカソビル1F A
TEL:03-5860-1622
「魚無双 トオダ」
東京都港区新橋4-15-6
TEL:03-5843-7370
【PR】
エスビー食品株式会社
読者の感想
興味深い0.0 | 役に立つ0.0 | 誰かに教えたい0.0
- 総合評価
-
- 0.0