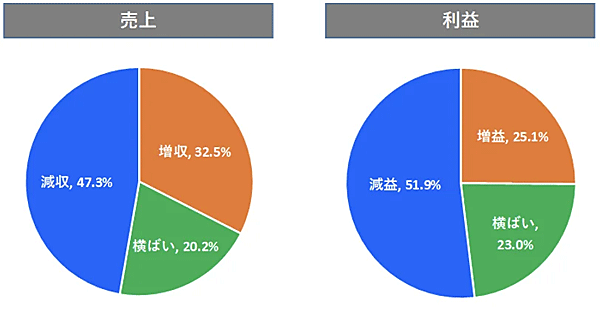<関連記事>

「コロナ禍をうまく切り抜けてきたのは『魚金』かも知れない」平成をリードした海鮮居酒屋の成長戦略とは
「酒場DI」、コロナ前に急回復。全産業の景気DIを抜いて、夏場に突入。
『肉汁餃子のダンダダン』は、なぜコロナ禍で40店も拡大できたのか。
コロナ前と比較し、「増収」の飲食店は35.2%だが、「増益」した飲食店はわずか25.1%にとどまった。要因として、物価高騰や光熱費の値上げなどが影響している模様。また、「減益」は51.9%という結果に。過半数の飲食店で利益が減少し、5類移行後も、苦しい経営状況が明らかとなった。コロナ前と比較した売上は、最も多かったのは「80%」で、コロナ前の売上に完全には戻っていない。
コロナ前後での実感を聞くと、客単価については、「美味しいものを求める傾向にあり、おいしいものにはお金をかけていただくことが多くなり、客単価が上がってきた。また、以前は低単価高回転で利益を得ていたが、高単価で低回転の営業戦略により利益を効率的に上げられるように工夫している。」 (埼玉県/居酒屋・ダイニングバー/3~5店舗)、「人件費、原価、支払手数料、水道光熱費等の高騰に合わせて単価を上げたので、客数自体は落ちたが売上が上がるという形になった。」 (神奈川県/焼肉/11~30店舗)と、外食好きの顧客は戻っている。しかし、なんとなく外食していた層は未だ来ない。
来店時間については、「早朝・深夜の来店が減って日中が増えた。」(東京都/カフェ/3~5店舗)、「2軒目文化が薄れた感じがする。」(東京都/バー/1店舗)、「来店時間が早くなり、滞在時間も短くなりました。」(神奈川県/洋食/1店舗)と、コロナでの外出を控えるという生活パターンから抜け切れていない。
他に、「コロナ禍で、在宅ワークが増えて今までの通勤動線から自宅近隣の飲食店に目を向けられるようになったのと、デリバリーをはじめて、こちらも認知されるようになり既存店への来店へと繋がった。」 (東京都/その他/1店舗)ろ、新しいマーケットやチャンスが生まれている。